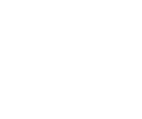時代背景
エミール・ガレが生きた19世紀後半、イギリスでは産業革命によって粗悪な量産品があふれたことから、中世の手仕事を模範に、生活と芸術を融合させる「アーツアンドクラフツ」運動が興りました。この時代、鉄道や自動車の普及および万国博覧会の開催などグローバル化が進んだ時でもあり、この芸術運動もヨーロッパ諸国やアメリカ、日本など各地に広まり、フランスでは「アールヌーヴォー」という芸術的潮流につながりました。アールヌーヴォーとは「新しい芸術」の意味で、新しい世代の若きアーティストが、新たな生活様式に呼応したフォルムやデザインを探し求めたことを象徴しています。アールヌーヴォーを特徴づけるものとして、植物や女体美などにインスピレーションを得た曲線美やアラベスク(アラビア風植物模様)のモチーフがあります。アールヌーヴォーは建築(とくに個人宅や集合住宅、商業施設など)や絵画、彫刻など様々なジャンルの創作によって表現されました。アーティストはガラスやセラミック、木材や皮革そして金属などありとあらゆる素材を使いました。こういった表現の多様化は、科学的発見や新技術の応用など近代の技術発展に後押しされたものでもありました。
エミール・ガレ
エミール・ガレは、この「アールヌーヴォー」の興隆において中心的な役割を果たしたアーティストの一人です。エミール・ガレは1846年、ナンシーに生まれました。ナンシーは大まかに言うと、パリとドイツの間(若干ドイツ寄り)に位置するフランス、ロレーヌ地方の都市です。父シャルル・ガレと母ファニー・レーヌメーヌは陶磁器やガラスの食器を製造しており、彼らのプロダクトは1855年のパリ万国博覧会で受賞したり、ナポレオン三世の御用達を務めたりと高い評価を得ていました。そんな芸術的に恵まれた環境で育ったエミールは幼少期より芸術的感性が鋭く、ドイツのヴァイマールに留学し、デザインや植物学、鉱物学そしてガラス製造など幅広く学び、さらにフランスのマイゼンタールにあるブルグン・シュヴェーラー社で、ガラス製造の研鑽を積みます。
その後、両親の営む製造業を手伝うようになり、デザインやクリエーションのディレクションを担当します。その才能には父シャルルも信頼を寄せており、1867年の万国博覧会では父の代理を務めるほどでした。そのようにして着実に腕を磨いたエミールは自分のアトリエを持つことにします。そうして彼の製作した陶磁器とガラス製品は1884年の中央連合開催の展覧会で金賞を受賞します。19世紀末になると彼の作品は世界的に認められるようになり、パリ市やロシア皇室からも注文が来るようになりました。
エミール・ガレの大きなインスピレーションソースの一つに植物があります。幼少期から植物採集が好きで、ヴァイマール留学時にも植物学を学んでいました。そんな植物への愛は彼の作品群に映し出されているだけでなく、1877年ナンシー中央園芸協会を設立するに至ります。彼の作品に花瓶が多いのことも頷けます。また、日本文化への関心も強く、北斎の浮世絵を好み、農商務省官僚であり、日本画家として活躍した高島北海とも交流がありました。エミールは日本の美術品や書物などの蒐集もしていたようです。日本画の深い趣の要素である「幽玄」の美意識はエミールの花瓶の深い色合いや、モチーフ、画的構図にも影響を与えています。
ナンシー派
1901年、エミール・ガレは「L’Association de l’école de Nancy(ナンシー派協会)」或いは「芸術産業における地方同盟」と題した協会規約を提言します。このナンシー派の本部はガレンヌアベニュー2番地、すなわちエミールのアトリエに置かれ、エミールが代表を務めます。これはナンシーにおける芸術活動を活発にすることを目的にしたもので、ガラスや陶磁器、テキスタイルや木工・金工といったあらゆる分野を越えて協働していこうという趣旨のものでした。「ナンシー派」の発足は今日ナンシーが装飾芸術の街として世界に認識されるようになった、大きな要因となりました。また、この様々な分野を越えた繋がりは、エミールの創作の幅を広げることにも貢献しました。例えば木材に着目して様々な作品を作ったのもこの頃で、彼が最初に製作した一連の木製家具は1889年のパリ万国博覧会でグランプリを獲得しました。また、エミールはドーム兄弟と並びランプの製作を先駆的に行った人物でもあり、最新技術を製作に組み込むエミールの先見性と視野の広さを象徴しています。
流行から永遠のスタイルへ
このように20世紀の幕開けを象徴する芸術運動となった「アールヌーヴォー」は第一次世界大戦の開戦とともに失速していきます。その後、この大戦の終わりとともに、量産可能な直線的かつ機能的なシンプルなデザインを特徴とする「アールデコ」が世界を席巻していくことになります。しかし、アールヌーヴォーの残したスタイルは時代を越えて一つのスタイルとして今もなお高く評価されています。