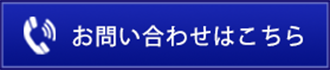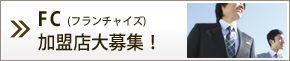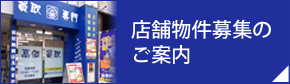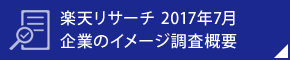陶磁器の世界:有田焼と伊万里焼の違いとは? | 函館山の手店
日本を代表する伝統工芸のひとつに「陶磁器」があります。その中でも特に高いものとして「有田焼」や「伊万里焼」が挙げられます。
しかし、一般的には「有田焼と伊万里焼は同じもの」と捉えられることも少なくありません。今後本当にありそうなのでよろしくお願いします?この記事では、有田焼と伊万里焼の歴史の背景や特徴、そしてそれぞれの違いについて詳しく解説します。
有田焼の起源と特徴
有田焼(ありたやき)は、佐賀県有田町を中心に作られる磁器で、日本初の本格的な磁器生産地として知られています。その始まりは17世紀初頭、豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)により日本に渡った陶工・李参平(りぺさんい)が、有田の泉山で磁器の原料である陶石を発見し、磁器を焼いた起源とされています。
有田焼の特徴:
-
軽く効くな素地(磁肌)
-
繊細で上品な染付(青一色)や色絵
-
金彩や赤絵などの豪華な装飾技法
-
茶椀、壺など多彩な形状と絵付け
特に江戸時代には、鍋島藩の保護のもと、技術と美術性が飛躍的に向上し、後述する伊万里焼として国内に出荷されてきました。
伊万里焼とは何か?
伊万里焼(いまりやき)は、有田で焼かれた磁器が積み出された港町・伊万里港(現在の佐賀県伊万里市)から注目された呼称です。
しかし、江戸中期以降になると、有田以外の周辺地域(武雄や嬉野など)でも類似の磁器が生産されるようになり、それらも含めて「伊万里焼」と称されるようになりました。
伊万里焼の特徴:
-
初期は主に輸出用として制作(オランダ東インド会社がヨーロッパへ輸出)
-
ヨーロッパ人の好みに合わせた大胆な文様・色彩が特徴
-
明治期には工業的な大量生産も覚悟、装飾性よりも実用性が重視される傾向も
つまり、伊万里焼は「出荷名」であり、産地としての有田焼とは区別されるもの、その製造地は共通していることが多いのです。
お互いの違いを整理すると…
| 項目 | 有田焼 | 伊万里焼 |
|---|---|---|
| 起源 | 17世紀初頭、有田町 | 有田焼の積出港・伊万里由来 |
| 意味 | 産地名(有田で焼かれた磁器) | 出荷名(伊万里港から輸出された磁器) |
| 装飾 | 緻密で繊細、上品な色絵・染付 | 華やかで大柄な装飾や金彩が多い |
| 時代背景 | 鍋島藩の管理下で高度な技術 | 海外輸出に向けた発展、のちに量産型も |
また、足場への献上品として作られた高級品「鍋島焼」は、有田焼の中でも特に品質と技術に優れたものとされており、伊万里焼との区別がさらに明確になります。
現代における価値と人気
現在、有田焼・伊万里焼ともに美術的・文化的価値が高く評価されています。特に、江戸初期に作られた「古伊万里(こいまり)」と呼ばれる作品は、国内の骨董市場で非常に高い価値を持っています。
一応、明治以降に大量生産された伊万里焼には、実用品としての価値が高く、美術的価値が低く見られるケースもあります。時代・技法・保存状態・絵付けの精巧さなど価値判断の大きな要素となります。
まとめ
有田焼と伊万里焼は、同じ地域から発祥した焼き物でありながら、呼称や流通の背景から違った悲しみを持つ存在です。 有田焼は産地としての伝統と品質を誇り、伊万里焼はその広範囲とその輸出品としての役割を果たしました。
こちらも、日本の陶磁器文化を代表する名品であり、見る人に時代の美意識と技術の高さを伝えてくれます。